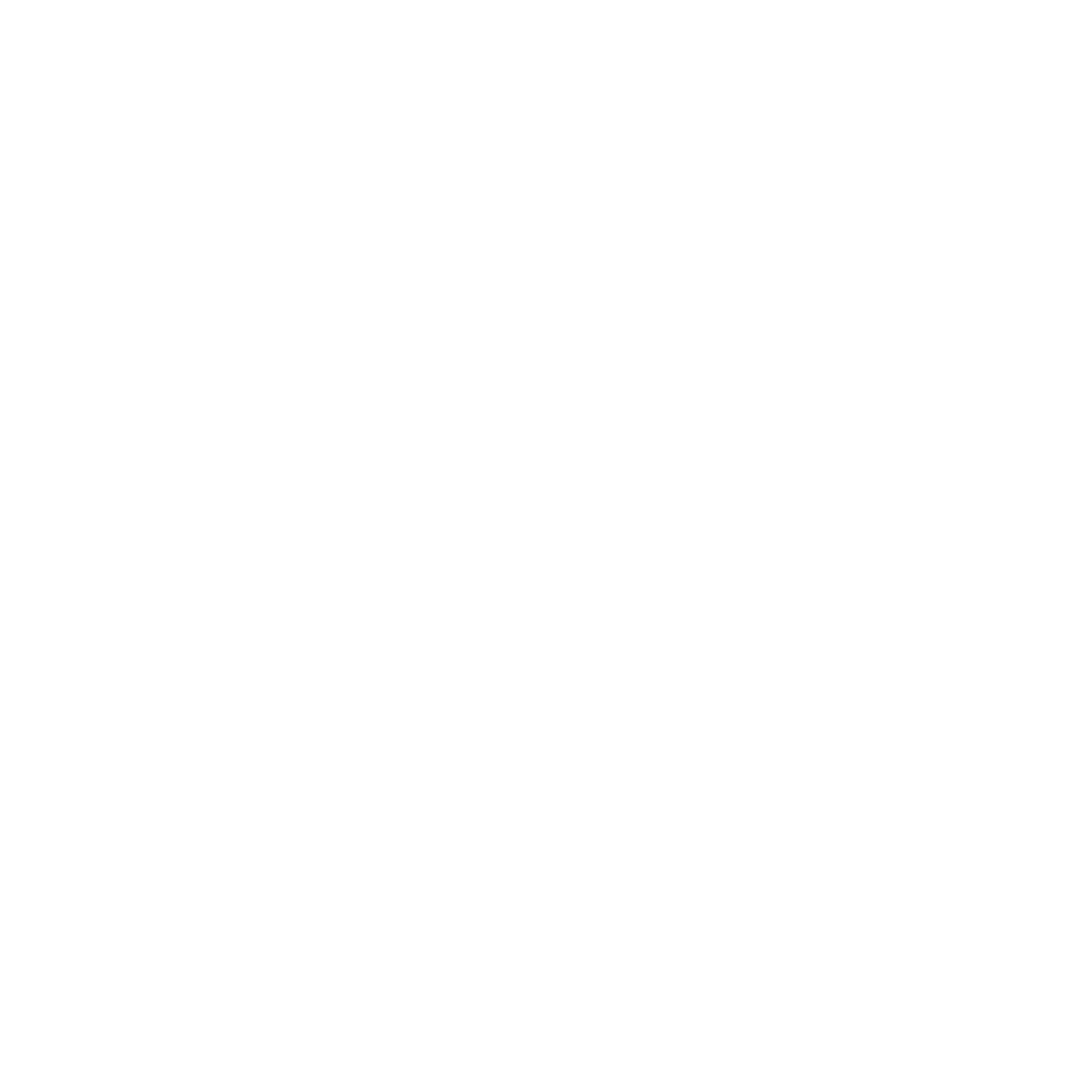
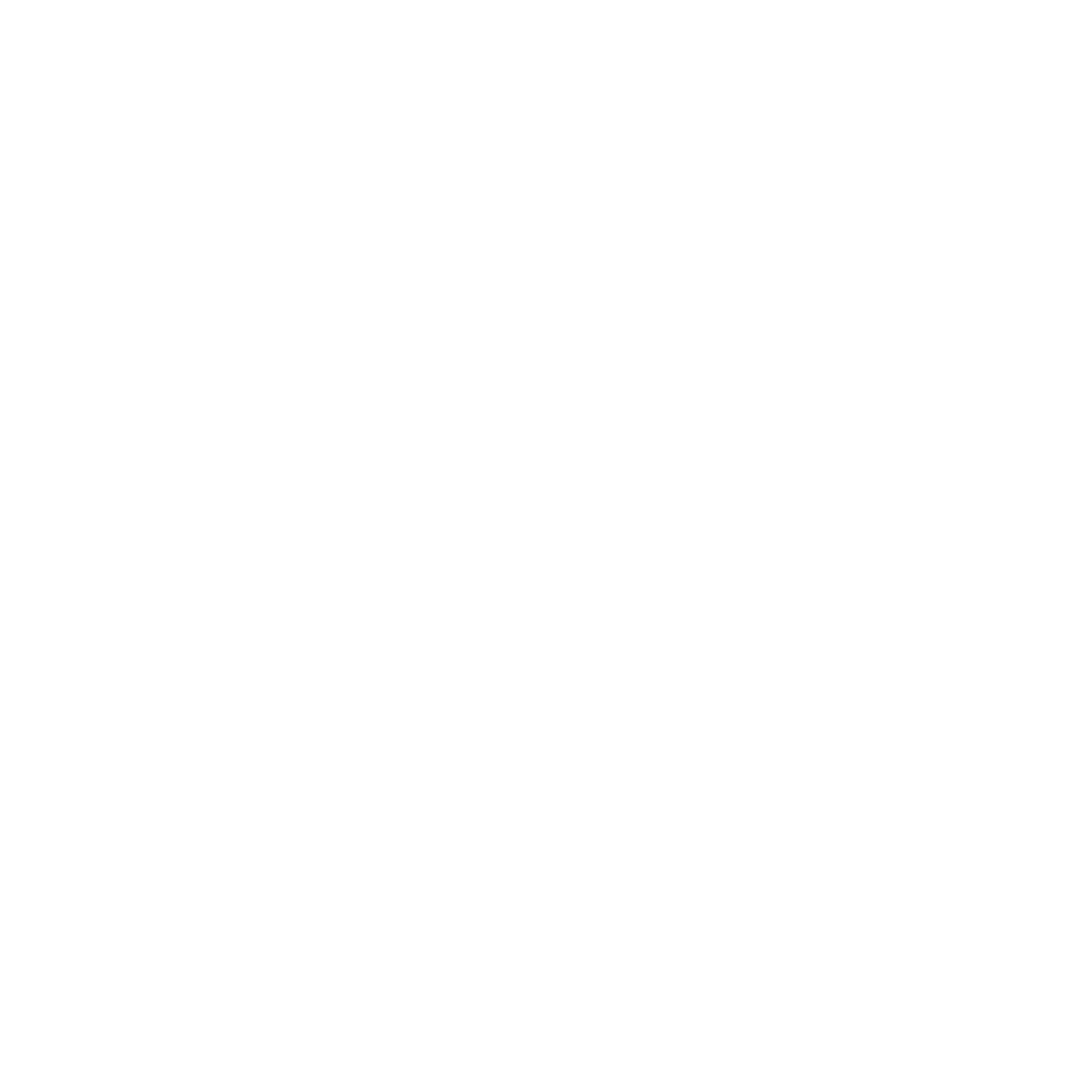
赤城 SUN do
〜ふたつの空と太陽の道〜

ヒカリへとつづく道、参道へ足をふみいれる。
石畳の階段をのぼり、鳥居を見上げ、一礼をする。よく仕上げられた白木の鳥居は艶やかに、その肌を輝かせて歓迎している。玉じゃりを踏む、リズムが喧騒をはがす。こんこんと湧く神池(しんいけ)が、静けさをうつ。土の香り。太陽は光のつぶを生み、風とともに木の葉をゆらす。
空気が変わる。
ここは、神のおわすところ。
のびのびと裾野へ引く稜線が関東平野を包み込むように、悠然とたたずむ赤城山。赤城神(あかぎのかみ)が鎮座するその山は、多くの生きものたちのいのちを育んでいる。山は水を湛え、生きものを潤し、木々は枝葉を大きく広げ、太陽の光を恵みにかえる。土はそんな木々を支え、枯れ葉や落ち葉を新しいいのちへと循環させる。
多くのいのちを育む赤城山は、いにしえより山そのものがご神体として崇められてきた。ときにカミナリの権現地として、神が鳴らす「神鳴り」とおそれられる一方で、稲妻は大地を豊かにし水の恵みとともに豊作をもたらした。そのような神がおわす山の中腹に、『赤城 SUN do』の舞台となる三夜沢赤城神社がある。

「神様は見えない、感じるもの。神社で気持ちを落ち着かせて、それを感じていただければと思います」そう語るのは、宮司の眞隅田吉行(ますだ よしゆき)さん。赤城神社の神官家(眞隅田家)84代目にあたる。三夜沢赤城神社は、全国に300社以上ある赤城神社の総本社の一つで、古来より農耕の氏神として信仰されてきた。
「例えば、神社にいて『気持ちいい』と感じることがありますよね。それは、神社と気が合っている、神社に歓迎されているということです。私たちは生まれながら神様の力をいただいているので、ここは合うとか、合わないという気の流れを感じとることができます。それはなんとなく感じているということではなく、神様と同じ力を持っているからこそ感じられるのです」。
眞隅田宮司は、毎朝6時過ぎに神社を開門する。参道の両脇には、天高くそびえる杉のご神木が連なる。朝の凜とした空気の中で参道を歩くと、ご神木から肌がピリピリするほど大きなエネルギーが感じられるという。
八百万の神は、草木にも、鳥けものにも、石や水や風にも、森羅万象にその姿を隠している。人の言葉を持たない彼らは、土の匂いや感触、木肌の触感、鳥の声や風のしらべにのせて私たちに語りかけてくる。その微細な呼びかけは、心地良さという衣を纏って、ふわりと姿をあらわすのだ。肌にふれて語りかけてくるそれらの存在は、地球があらゆるものとともに生きていることを教えてくれる。
「神様がいなくなることを『神上がり(かみあがり)』と言いますが、私は皆さまが気にいっているこの神社を決して汚したくない。神様が気持ちよくいられるようにこの神社を守っていきたいと思っています」。 すみずみまで掃き清められた境内には澄んだ空気が流れる。自然の風化に任せないその手しごとは、混沌に節度をかけ、礼をもって祓い清めようとする眞隅田宮司の覚悟があらわれていた。

一昨年、宮司であった父が他界した。しかし亡くなった今でも、眞隅田宮司は父の存在を近くに感じているという。他界してしばらくたった頃、社殿で祈祷をしていると、祝詞をあげていた父の姿がふと思い浮かんだ。そのとき初めて、小さい頃から祝詞をあげる父の背中をみて学んできたことに気がついた。父の背中には、一切手を抜かず神職を全うしようとする宮司としての覚悟が宿っていた。その覚悟はいま、眞隅田宮司に受け継がれている。
「父からの教えとしては、日々の行いすべてが教えでしたね。父は神社の本来の姿をとことん追求している人でした。父には申し訳ないですけれど、父の病気を宣告されたときは、父が亡くなる寂しさより私はこの神社を背負っていけるのであろうかという恐怖感がものすごく強かったですね。だからこそ、宮司として父の跡を継ごうと決心した時の覚悟が大きかった。皆さまが気に入っているこの屋代を守っていく。神職の責務を全うできるよう神様と参拝者の方の仲をとりもってその願いを伝えていきたいと思っています」
父の背中越しにみえた覚悟は、代々、赤城神を守ってきた先人たちの歴史でもある。何千年という時を経て神を守り、人々の心の拠り所となる祈りの場を守ってきた。先人たちのたゆまぬ思いによって、鎮守の杜で育まれる生きものたちと同じように、私たちの心もまた、守られ育まれているのだ。
社務所には、生前に父がいつも座っていたイスがそのまま残されている。イスは空席のまま、静かに二人をつないでいる。

カナダ・ユーコン準州ホワイトホースは、オーロラが頻繁に発生する地帯「オーロラベルト」の真下に位置するユーコン川のほとりにたたずむ穏やかな州都だ。『赤城 SUN do』では、ホワイトホースと中継をつなぎ、現地の神秘的なオーロラをリアルタイムで赤城神社の空に灯す。
ユーコンは大自然による神秘で溢れている。極地方の夜空を彩る幻想的なオーロラは、太陽と地球のせめぎ合いから生まれる惑星規模の現象だ。氷河を抱いて峻立する山々、大地をゆったりと流れる大河が悠久のときをしのばせる。〈ウィルダネス〉と呼ばれる手つかずの自然が州土の約8割を占め、人間より野生動物が土地の主役となっている。一年の半分が冬となる厳しい環境下でも、生きものたちは〈食う食われる〉という生〈せい/なま〉のダイナミズムを繰り広げながら、いのちをつないでいる。

地球的な循環のダイナミズムは、西洋化された現代社会とは明らかに違う、大きな流れのメトロノームを刻む。この土地に生きる先住民は、そのリズムを敬いながら、自然とともに狩猟採集生活を営んできた。
自然を敬うこと、祈りを捧げること。生きものの生命をいただくこと、魂は自然に還すこと。恵みを平等に分かち合うこと、助け合うこと。先住民の教えは、現在も、古き良きカナダの面影としてあらわれ、互いに助け合い、分かち合う精神が、良質な人とのつながりとしてユーコンの人たちに息づいている。
土の匂いや感触、木肌の触感、鳥の声–––感受性を通じて働きかけてくるこれらの感覚は、情報として理解する世界から、世界を混じりけなく、それでいて深く、リアリティの中でありのままにその存在を受け入れている。この感覚が、自然と分断された世界の脆さ、はかなさへの気づきをうながし、地球時代を生きる私たちへのヒカリの灯火となってくれるだろう。
Text by Nozomi Suzuki